
福間香奈女流六冠、2度目の棋士編入試験資格を獲得
2025年10月6日、福間香奈女流六冠が棋士編入試験の受験資格を再び獲得しました。2022年以来、2度目の資格獲得となります。受験するかどうかについては現在検討中で、合格すれば史上初の女性棋士誕生となります。
棋士編入試験の受験可否は、資格獲得後1か月以内に決断する必要があります。福間女流六冠は「前向きに検討したい」とコメントしています。
西山朋佳白玲、クイーン白玲へ王手
ヒューリック杯第5期白玲戦七番勝負第6局が、10月18日(土)に石川県金沢市「ホテル日航金沢」で行われ、西山朋佳白玲が110手で福間香奈女流六冠を破り、4勝2敗でタイトル防衛を果たしました。
この防衛により、西山白玲は通算4期目の白玲位を獲得。次期も防衛すれば通算5期となり、「クイーン白玲」の称号を得ます。クイーン白玲の達成者には「棋士(四段)」への昇段と、フリークラス編入資格が付与されます。
女流棋士、三強時代へ突入

筆者は、現在の女流将棋界が「三強時代」に入ったと見ている。
これまで女流棋士界を牽引してきたのは、福間香奈女流六冠と西山朋佳白玲の二強だった。そこに新たに加わったのが、2024年11月に女流棋士へ転向した中七海女流三段である。
この三人はいずれも元奨励会員で、年齢制限により三段で退会したという共通点を持つ。すなわち、四段昇段には届かなかったものの、実力的にはそれに極めて近いレベルの女流棋士たちだ。
棋士と女流棋士の違い
「棋士(四段以上)」と「女流棋士」は明確に区別され、それぞれ別制度で運営されている。最大の違いは、棋士は性別を問わないのに対し、女流棋士は女性限定の制度である点だ。
棋士を目指す者は、まず奨励会に入会し、三段リーグで上位に入ることで四段に昇段する。制度自体に性別の制限はなく、男女平等の仕組みといえる。
一方で、これまでの歴史の中で女性が三段リーグを突破した例はない。そのため、日本将棋連盟は女性の活躍の場を広げる目的で、女流棋士制度を設けた。筆者は、この制度を「公平な奨励会制度に対する補完的な仕組み」と位置づけている。
西山朋佳を想定した「クイーン白玲ルート」誕生

2025年6月6日、日本将棋連盟の通常総会で「羽生案」が可決され、女流棋士が特例として四段相当と認められる新制度「クイーン白玲ルール」が成立した。
同日、清水市代女流七段(56)が新会長に就任。四段経験のない女流棋士が、四段以上の棋士を統括する初の体制となった。この人事は、プロ野球で中学生の女子選手が監督に就任するようなもので、将棋界でも前例のない出来事として注目を集めている。
また、同総会では藤井聡太七冠が「棋力の担保は取れているのですか?」と疑義を呈したと報じられている(週刊新潮より)。
透けて見える将棋連盟の狙い
筆者の見立てでは、日本将棋連盟は「女性棋士(女流棋士ではなく、正式な棋士)」をどうしても誕生させたい意向があると考えられる。奨励会ルートから女性が棋士になるのは現実的に難しいと判断し、白玲通算4期の西山朋佳白玲を想定して「クイーン白玲ルート」を整備したのではないか。
現在、西山白玲は通算5期(クイーン白玲)達成を目前としており、制度上、達成すれば自動的に棋士(四段)資格を得る見込みだ。
一方、福間香奈女流六冠には、棋士編入試験を再び受験する可能性が残されている。しかし、過去に受験して不合格となっており、再挑戦しても合格は容易ではないだろう。
棋士編入試験の試験官は、当該年度に奨励会から昇段した新四段が務める。彼らは当然、強い自負を持ち、「三段リーグを突破できなかった者が受験してくるのか」と対抗心を燃やす可能性が高い。そうした背景もあり、福間女流六冠が合格を勝ち取るのは容易ではないと見られる。

【新ルール】クイーン白玲(通算5期)で四段昇段!将棋界に激震走る
将棋界で、女流タイトル「クイーン白玲」達成者に棋士フリークラス編入資格を与える案が浮上。三段リーグや編入試験を経ない女性限定ルートの新設に、制度の根幹を揺るがすとの懸念が噴出。公平性や棋力差を巡る議論が巻き起こっている。
歴史的転換点となった2025年6月6日

2025年6月6日、日本将棋連盟は歴史的な一日を迎えた。
この日、通常総会において「羽生案」と呼ばれる制度改革案が可決され、女流棋士のトッププレイヤーに対し、特例として四段昇段およびフリークラス編入資格を付与する新制度「クイーン白玲ルール」が正式に成立した。
これは、従来の昇段ルートである「奨励会三段リーグ」や「棋士編入試験」に加え、女流棋士の実績と実力を評価する新たな道として注目されている。
同日、長年にわたり女流将棋界を牽引してきた清水市代女流七段(56)が日本将棋連盟の会長に選出された。女流棋士が会長に就任するのは史上初であり、しかも清水氏は四段経験を持たない立場から全棋士を統括することとなった。この前例のない人事は、将棋界に大きな衝撃を与えた。
この出来事は、多様性と門戸開放の象徴として歓迎される一方、伝統や序列を重んじる立場からは懸念の声も上がっている。清水新会長が、こうした期待と反発の入り交じる中でどのように舵を取るのか――その手腕が今後の将棋界の方向性を左右するだろう。
棋士と女流棋士の制度的な違い
日本将棋連盟に所属するプロは、「棋士(四段以上)」と「女流棋士」に明確に区分されている。
棋士になるには、若手育成機関「奨励会」に入会し、厳しい昇段規定を経て三段リーグを突破し四段へ昇段する必要がある。または、棋士編入試験に合格し、四段相当の実力を認められる方法もある。四段昇段後は性別を問わず正式なプロ棋士として認定され、順位戦などの公式リーグに参加できる。この制度は完全な実力主義であり、男女の区別は存在しない。
一方、女流棋士は女性限定の制度で、主に以下の3つのルートで資格を得る。
- 女流育成機関
- 日本将棋連盟の研修会で一定の成績を収める
- 奨励会に所属していた女性が退会後に転向する
前例なし!
ただし、連盟の100年以上の歴史の中で、女性が四段に昇段して正式な棋士となった例は一度もない。制度上は男女平等であっても、実際には極めて高い壁が存在しているのが現状であり、そのため「女流棋士」という枠組みが設けられている。
清水市代新会長と将棋界の行方
こうした背景を踏まえると、清水市代女流七段が四段経験を持たないまま日本将棋連盟会長に就任したことは、制度面でも歴史的にも極めて象徴的な出来事である。
そして、清水新会長の体制下で「クイーン白玲ルール」による女性棋士が誕生すれば、それは日本将棋連盟における真の転換点として、将棋界の新たな時代の幕開けを意味するだろう。

【将棋】女流棋士は棋士ではないについての考察、プロ棋士とは?
2024年6月16日、女流棋士発足50周年記念パーティーが開催され、YouTubeでも公開。羽生会長の挨拶、藤井八冠のビデオレターなどがありました。中井女流六段は「打倒藤井八冠」を掲げました。
図解:日本将棋連盟のヒエラルキー

清水市代女流七段が日本将棋連盟会長に就任するということが、どれだけイレギュラーなことなのかは、以下の図で理解できるはずだ。
会長は正会員から選出される
*清水会長は日本将棋連盟の正会員であるが、四段昇段経験はない。
- 正会員 … 棋士(四段以上、女流四段以上またはタイトル経験者)
- 準会員 … 奨励会員(6級~三段)
- 賛助会員 … アマ強豪・普及指導員など
- 女流棋士会員 … 女流棋士(女流2級以上)

図の説明
- 名人
A級リーグで優勝した棋士は名人への挑戦権を得る。挑戦者と名人が7番勝負を行い、勝者が新たな名人となる。敗者はタイトルを失ってもA級に残り、次年度はA級リーグの序列1位に編入される。
- 順位戦
順位戦はA級からC級2組までで構成され、年度ごとにリーグ戦形式で行われる。各組で上位の成績を収めれば昇級し、下位に沈めば降級となる。A級は最上位のため昇級はなく、1位の棋士のみが名人への挑戦権を得る。B級1組以下には名人挑戦の資格はない。
- フリークラス
C級2組から降級するとフリークラスに編入される。または、棋士編入試験に合格すると、フリークラスに編入される資格を獲得する。フリークラスは順位戦に参加できない。フリークラス所属の棋士は、10年以内にC級2組へ昇級できなければ引退 しなければならないという規定がある。
- 奨励会
奨励会三段リーグは年に2回(半期ごと)行われ、そこで成績上位2名に入ると、奨励会を卒業して四段に昇段し、正式な棋士(プロ)として活動することが認められる。さらに、日本将棋連盟の順位戦においては C級2組から編入され、プロ棋士として公式戦に参加する権利を獲得する。
- 棋士編入試験
棋士編入試験に合格すると、奨励会を経ずに四段に昇段し、正式な棋士(プロ)として活動することが認められる。この場合は、順位戦には参加できないフリークラスからの参加となる。
- 女流棋士
将棋の奨励会に入会し、三段リーグ以下の成績で退会した女性は、日本将棋連盟が定めた基準を満たすことで、女流棋士としてプロ活動が認められる場合があります。また、奨励会ではなく、女流棋士育成機関である研修会(旧:女流育成会)で規定の成績(女流2級の基準)を収めた場合も、女流棋士2級の資格を得ることができます。

四段経験なしで全棋士を統括!清水市代新会長が将棋界にもたらす衝撃
2025年6月6日、清水市代女流七段が日本将棋連盟の新会長に就任しました。四段経験のない女流棋士が全棋士を統括する異例の人事で、将棋界に衝撃が走っています。新制度「クイーン白玲ルール」の成立と同日の就任は、多様化と伝統の間で注目されます。また、過去に理事を解任された片上大輔氏が再任された点も波紋
まとめ


今回の記事では、2025年6月6日の日本将棋連盟における歴史的な出来事を中心に、将棋界の現状と今後の展望について考察しました。
この日、女流タイトル保持者に特例で四段昇段資格を与える「クイーン白玲ルール」が成立し、同時に四段経験のない清水市代女流七段が連盟史上初の女性会長に就任するという、二つの大きな変革が同時に起こりました。この異例の体制は、伝統と序列を重んじる将棋界において、多様性と門戸の開放を象徴する出来事です。
また、現女流棋士界は、元奨励会三段である福間香奈女流六冠、西山朋佳白玲、そして2024年11月に転向した中七海女流三段の「3強時代」に突入したと筆者は見ています。
特に注目されるのは、白玲通算4期である西山白玲の動向です。次期防衛で「クイーン白玲」の永世称号を獲得し、そのまま新ルール適用による史上初の女性棋士が誕生するのか。あるいは、福間女流六冠が二度目の資格獲得を活かし、棋士編入試験に挑むのか。
いずれのルートにせよ、連盟が長年果たせなかった「女性棋士の誕生」が現実味を帯びてきています。清水新会長のリーダーシップのもと、将棋界がこの歴史的な転換点にどう対応し、未来を切り開いていくのか、今後の展開から目が離せません。
このサイトを検索 | Search this site




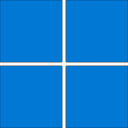









0 コメント