
お賽銭は語呂合わせ?
神社参拝の際、賽銭箱へ入れるお金の金額を語呂合わせで決めることがあります。
例えば、「五円玉=ご縁がありますように」「50円玉=ご縁が10倍ありますように」といった具合です。
しかし、お賽銭の語呂合わせとご利益の相関関係については、大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)を祭神とする出雲大社が公式見解を示しています。
「いずもたいしゃ」として広く知られる出雲大社ですが、正式名称は「いづもおおやしろ」と読みます。縁結びや八百万の神々が集まる神社として有名な出雲大社は、今回、語呂合わせを信じる参拝者や観光ガイドに対し、警鐘を鳴らしました。
出雲大社の衝撃の回答とは?
出雲大社「語呂合わせに根拠はない」
これだけでは物足りないと感じる方もいるでしょうから、一般的にどのような語呂合わせが使われているのか、以下で紹介します。
お賽銭の金額は決まっていますか?
出雲大社の衝撃の回答を引用します。
お賽銭を5円にすると「ご縁がある」とか、「二重にご縁があるように」と25円、「始終ご縁があるように」と45円、「これ以上の硬貨(こうか=効果)はない」と500円などと、ガイドの方がおもしろおかしく話を作って案内されるのを聞くことがあります。
これは、まったく根拠のないおもしろおかしくしようとの“ためにする”語呂合わせにすぎません。大切なのは神様に対して真摯な気持ちでお祈りをし、その気持ちをもって日々の生活を送ることです。
祈りの心はお賽銭の金額によって、まして変な語呂合わせで左右されるものではありません。
よくあるご質問 | 出雲大社お賽銭の語呂合わせ

筆者が調べたところ、お賽銭にまつわる語呂合わせには、以下のようなものが存在しました。
出雲大社はこれらをすべて「迷信であり、根拠がない」と明言していますが、長年にわたってこうした言い伝えに親しんできた筆者にとっては、その一言で簡単に割り切れるものではありません。
たとえ「科学的・宗教的根拠はない」と言われても、神社に参拝すると、つい無意識に5円玉や50円玉を財布の中から探してしまうのです。
| お賽銭 | 語呂合わせ | 判定 |
| 5円 | 「ご縁」がありますように | 迷信 |
| 2×5円 | 「重ね重ねご縁」がありますように | 迷信 |
| 4×5円 | 「よいご縁」がありますように | 迷信 |
| 6×5円 | 「安定と調和のとれたご縁」がありますように | 迷信 |
| 8×5円 | 「末広にご縁」がありますように | 迷信 |
| 10円 | 「遠縁」:縁を遠ざける | 迷信 |
| 15円 | 「十分なご縁」がありますように | 迷信 |
| 20円 | 「二重のご縁」がありますように | 迷信 |
| 21円 | 「別れない」:割り切れない数字 | 迷信 |
| 25円 | 「二重にご縁」がありますように | 迷信 |
| 35円 | 「再三ご縁」がありますように | 迷信 |
| 45円 | 「始終ご縁」がありますように | 迷信 |
| 50円 | 「ご縁が10倍」ありますように | 迷信 |
| 55円 | 「五重のご縁」がありますように | 迷信 |
| 65円 | 「ろくなご縁」がない | 迷信 |
| 75円 | 「何のご縁」もない | 迷信 |
| 85円 | 「やっぱりご縁」がない | 迷信 |
| 500円 | 「これ以上の効果はない」:硬貨≒効果 | 迷信 |
参拝の作法

神社本庁公式サイトで参拝の作法を見つけたので、紹介します。
[3つの作法]
- 手水の作法
- 拝礼の作法
- 玉串拝礼の作法
3つの作法は以下の通り。
1. 手水の作法
出典:参拝方法 | 神社本庁先ず、手水舍(てみずや)の前に立ち、水盤に向かい、「心身の浄化」のために手水を行うことが最も大切です。
- 右手で柄杓ひしゃくを取ります。
- 水盤の水を汲み上げ、左手にかけて洗います。
- 柄杓を左手に持ち替え、水を汲み上げ右手を洗います。
- 再び柄杓を右手に持ちかえて、左手のひらに水を受けて溜めます。
- 口をすすぎます。柄杓に直接口をつけないようにしましょう。静かにすすぎ終わって、水をもう一度左手に流します。
2. 拝礼の作法
出典:参拝方法 | 神社本庁
神社での参拝方法は、二拝二拍手を基本としていますが、神社によっては特殊な拝礼方法を行っているところもあります。
- 神前に進み姿勢をただします。
- 背中を平らにし、腰を90度に折り、拝をします。この時の拝は2回行います。
- 胸の高さで両手を合わせ、右指先を少し下にずらします。
- 肩幅程度に両手を開き、2回打ちます。
- 指先を揃えます。最後にもう1回拝をします。
*注:伊勢神宮や出雲大社は二拝四拍手一拝です。
3. 玉串拝礼の作法
出典:参拝方法 | 神社本庁
神社で祈願するときやお祭りをおこなうときには、神さまに玉串という榊(さかき)の枝を捧げます。
玉串は、みずみずしい榊の枝に木綿(ゆう)、紙垂(しで)といわれる麻や紙を取り付けたものです。
- 右手で榊の元(根本)の方を上から、左手で先の方を下から支え胸の高さに、やや左高に、少し肘を張って持ちます。
- 玉串の先を時計回りに90度回します。
- 左手を下げて元を持ち、祈念をこめます。
- 右手を放して、玉串をさらに時計回りに回し、玉串の中程を下から支えます。
あとがき

団体客が出雲大社に参拝する際、引率のガイドがお賽銭の語呂合わせの由来を説明している現状があるようです。
このことから、出雲大社に限らず、伊勢神宮のようなガイド付きの団体客が参拝する他の神社でも、同様に語呂合わせを信じる人々が多数生み出されていると考えられます。
しかし、出雲大社は公式にこの語呂合わせについて「根拠なし」と清々しいほどにきっぱりと否定しています。
そうなると、語呂合わせを信じて案内してきたガイドの立場は一体どうなるのでしょうか……?
まとめ


神社に参拝する際、多くの人がお賽銭の金額を語呂合わせで決める習慣があります。
例えば、五円玉には「ご縁がありますように」、五十円玉には「ご縁が10倍ありますように」といった願いを込めることが一般的です。しかし、これらの語呂合わせが実際にご利益と関連があるのかという疑問に対し、縁結びの神様として有名な出雲大社が明確な回答を出しました。
正式名称を「いづもおおやしろ」と読む出雲大社は、この度、お賽銭の語呂合わせを信じる人々、さらには参拝ツアーのガイドに対しても警鐘を鳴らしました。
その結論は非常にシンプルで、「語呂合わせに根拠はない」というものです。つまり、お賽銭の金額とご利益の間には、語呂合わせによる直接的な関係性はないと、出雲大社が公式に否定したことになります。
このサイトを検索 | Search this site




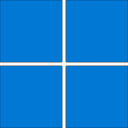









0 コメント